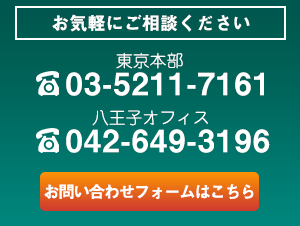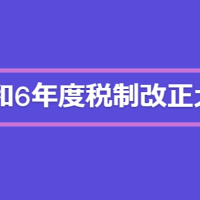すっかり秋の陽気になり、心地よい風が感じられる今の季節が非常に好きです。
さて、前回からの続きを書いていきたいと思います。(前回の記事を読まれていない方はまずそちらをお読みください)
②については、社会における格差が拡大することはよくないことであるということは皆さん理解していらっしゃることと思いますが、例えば累進課税制度により所得の高い人には多く課税し、所得の低い人には少なく課税することで所得の格差を是正します。
また、徴収した税金を社会保障制度として使うことで、再分配を行います。
➂は景気が過熱しているときには多くの税金を徴収し、不景気の時には税金の徴収を少なくすることにより変動幅を安定化させるものです。
例えば、法人税や所得税の場合、好景気で所得が大きくなったときは多くの税金を納めますが、一方で、所得がマイナスになった際は1円も税金を納めずに済みます。
ここで一つの疑問が浮かんできた方もいらっしゃるかもしれません。消費税です。
生きていくうえで必要なものを消費する際に課せられる消費税は、いわば消費に対する罰金です。
消費税は好不況関係なく、また、高齢者や子供たち、はたまた病人などからも容赦なく徴収されてしまいます。
好不況関係なくすべての人に課せられる消費税は、安定的な財源としてその重要性が高まってきている状況ですが、好景気の時ならまだしも、不景気の時にはより一層消費を冷え込ませることにつながりかねません。
高所得者と低所得者では所得のうち、消費に回す金額が占める割合も異なり、負担率で考えると高所得者は低負担で、低所得者は高負担(所得の多くを消費に回すため)となっており、格差がより拡大してしまう逆累進課税の性質をもった税金であるといえます。
したがって上記①の役割には大きく貢献しているものの、②③に対しては妨げとなっているものなのです。
個人的な意見ですが、私は税金の役割としてより重要なものは①ではなく②や➂だと考えています。
経済成長をして、法人や個人が儲かることにより、その儲けに対する税収が増えていくことが理想的であり、目指すべきところではないでしょうか。